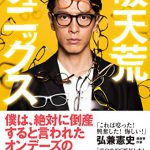※昨晩の北海道神宮
人生を豊かにする仕事の辞め方
皆さん、ごきげんよう。
北海道札幌市中央区の税理士 板倉圭吾です。
今日は仕事の辞め方について。
昨今のコンプライアンス意識では当然ですが、労働者の権利を行使させないと退職トラブルを招いてしまいます。
今日お伝えしたいのは、それとは視点を変えて。労働者側として、「辞める時に考えていたこと」の一例についてです。
要は、「私が組織から離れるときにはどういう感じだったのか」という記事です。
(税理士が顧問契約解除となる際の作法については、税務弘報に寄稿しております)
①銀行を退職した時
まだ一人前とは呼べない、入行2年目(2001年)に銀行を退職しました。
退職理由は、「小樽商科大学の卒業論文で取り組んだ労働法に関わる公務員になりたい」というものでした。
当時の支店長や副支店長などからは慰留されましたが、銀行員としてキャリアを続けることの限界を感じたというのが本当のところです。
しかし、退職を認めていただける(本当にこの表現が正しいニュアンス!)ことになり、「これから板倉が行政組織に入るのであれば、公務員として役立つ経験を退職までの期間で与えよう」と言ってくださいました。「その代わり、退職時期については銀行に一任してほしい」とも。
そこで、公金融資などの新規業務を経験をさせていただき、(前任は作ってくれなかったのでイチから)私なりの引継書を作成して、退職日を迎えました。
当然(だと当時は思っていたの)ですが、有給休暇の消化はできません。1日も。
でも店舗2階の会議室で、ささやかに開いていただいた送別会(月末の打ち上げを兼ねていた…)は忘れられません。
厳しい金融の世界から離れられる安堵と、銀行のバッジがなくなる不安と…
20年ちょっと前のことです。
今とは隔世の感がありますね。
②公務員を退職した時
公務員の退職は2015年の12月です。
2014年12月の官報に税理士試験合格者として掲載され、10日ほど後の北海道新聞にも「道内関係合格者」として氏名が掲載されました。
(税理士試験受験生だった頃は、新聞に掲載されることにステータスを感じたものです。)
当然、官僚幹部や同僚にも合格が知られることとなり、廊下で会った方に「いつ辞めるの?」と聞かれることもしばしば。
職場には内緒で受験をしていたので、多くの方に驚きを与えてしまったようです。
ただ、その時に考えていたのは、「育児休業で周囲の協力も得たのだから、合格が判明してから1年間は恩返しをしよう」というものでした。
最終的には2015年9月に退職の意向(2015年12月で退職)を署長に伝えました。
年度の途中でしたが、代替職員の確保が見込めることが確実な状況でした。
「年休を消化しないので、年度途中の退職ではありますが、迷惑をできるだけおかけしません」とお話したのを覚えています。
公務員は、その時代でも「退職願」を全文直筆で書く必要があり、それを受けて「辞職を承認する」という辞令を受け取りました。
2015年の仕事納めまで働き、2016年の年明けからは税理士事務所での新しいキャリアをスタートさせました。
③きれいな辞め方が人脈になる
『「育児も税理士としての価値提供も妥協しない税理士」として生き続けるための戦略』セミナーを受講された方には詳しくお伝えしておりますが、開業後の税理士としてのお客様には、銀行や公務員時代の先輩や同僚、そのお知り合いをご紹介いただくケースも多いです。
当時の仕事ぶりや、辞め方などを知っている方が、「板倉なら任せられる」と連絡をくださるのです。
仕事に直結しなくても、近況報告する機会を設けてくださるなど、気にかけていただけることがありがたい。
人生を豊かにしてもらっているな、と感じます。
④今、仕事を辞めたいと思っている方に
この記事は労働者の権利を行使しないことを勧めているのではなく、n=1の退職のリアルを書いたものです。
その後の私の人生に与えてくれた影響を考えて、振り返ってみると、「職場の同僚に負担を強いない辞め方をして良かった」と思っています。
2年足らずしか在籍していない銀行の先輩から、大切な仕事を任せていただける。
国家公務員としてのかつての振る舞いで、税理士としては経験が浅いうちから信頼してもらえる。
そのような印象を残す辞め方もあるよ、ということです。
※もちろん理不尽な経営者側の要求に対しては、労働基準監督署や弁護士などと相談して対応してくださいね
【編集後記】
板倉事務所の確定申告は1週間前に終わりました。
支払調書や償却資産税の申告も期限前に終わっています。
税理士の繁忙期対策は、「締切りより圧倒的に早く終わらせる」という意識ではないでしょうか。
周到な段取りと、納税意識の高い方を選んでお役立ちすること。
そのためには、「しっかりとした仕事をする」という評価を得て、選ばれる努力が欠かせません。